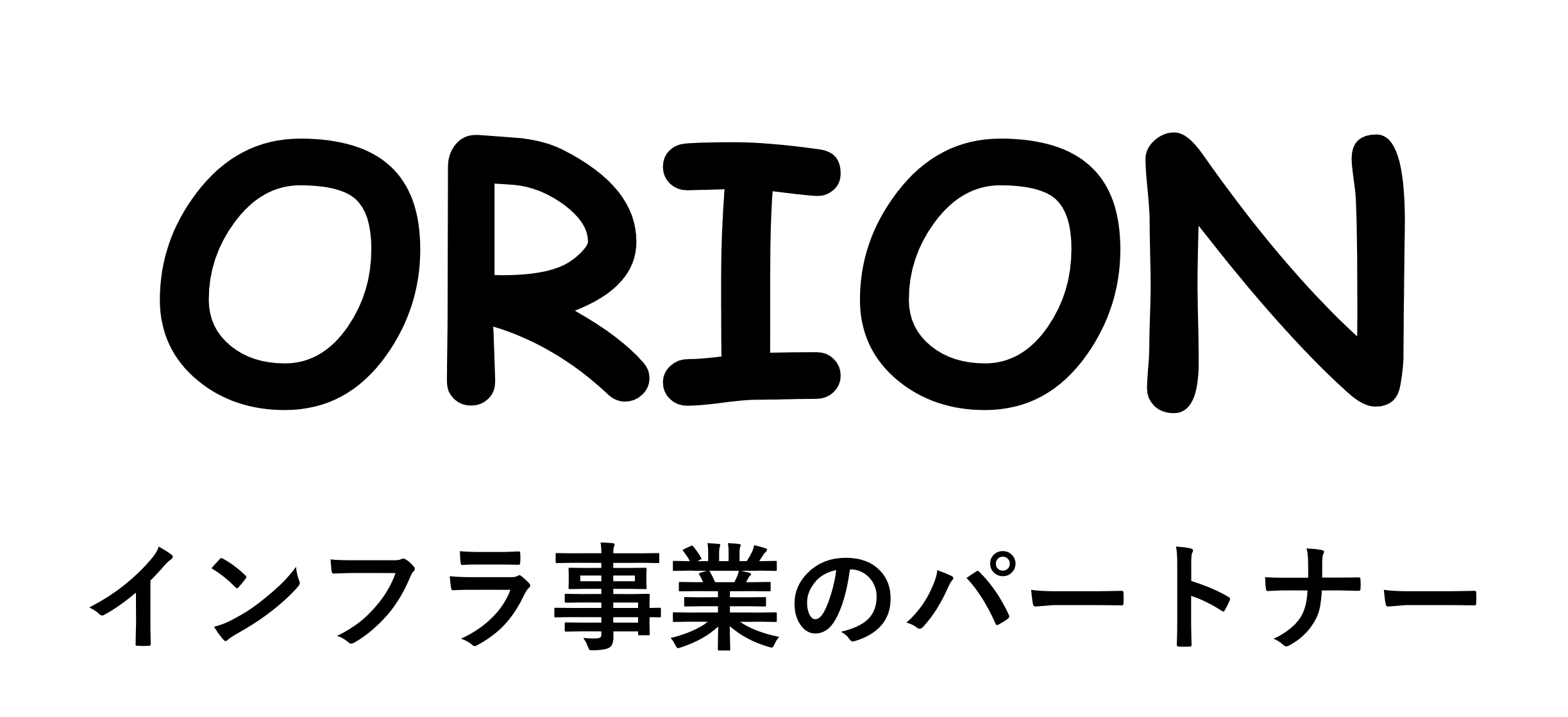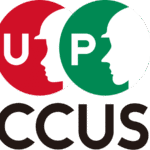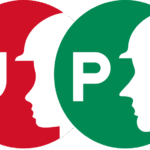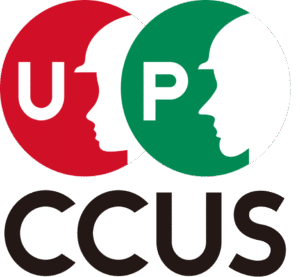建設業許可申請というものは、多くの要件があり、内容も複雑で、要件に関してはそれを根拠付ける資料の提出等があります。
提出書類はというと、確認資料も含めると40枚以上になることもあります。
申請に関しては、複雑ですが、昨今の工事現場では、許可の取得業者でなければ仕事を請けられない現場もあるようで、許可の要否に関しては、請ける工事の金額関係なく取られる事業者様も多い印象です。
-

-
【技術者の違い】直接的恒常的 監理技術者等、営業所技術者、経審
建設業に関する「技術者」とはいくつかの種類が存在します。今回は、この「技術者」の違いについてまとめます。 技術者と一言にいっても、建設業許可要件でもある「営業所技術者」、配置技術者の「主任技術者」「監 ...
続きを見る
-

-
【CCUS】「技能者を大切にする企業」の自主宣言制度とは 経審
2024年6月20日に開催された建設キャリアアップシステム(CCUS)処遇改善推進協議会で、CCUSの現場利用拡大に向けた3か年計画案として3つの大きな取組案が提示されました。 この計画案の中に、「技 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】国家資格で多くの業種を取得するメリットデメリット
建設業許可の要件の一つして、「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」を置かなくてはならないとされています。 関連:建設業法第七条第二項 つまり、「営業所技術者」のこ ...
続きを見る
-

-
【建設業法】連絡員とは 改正による専任特例における現場配置
今回は、建設業法の改正に伴って新たに規定された専任特例制度における「連絡員」について解説します。 連絡員とは、専任特例制度を利用した際に、現場配置が求められる技術者のことを指します。 では、この連絡員 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】特例監理技術者とは 監理技術者補佐(専任特例2号)
特例監理技術者という言葉を耳にしたことはございますか? 今回は特例監理技術者とはどのようなものかを説明します。 監理技術者とは そもそも監理技術者とはなにかというと、いわゆる特定建設業での現場に配置す ...
続きを見る
-

-
建設業者の支払い期日とは 下請法との違い
下請け契約を締結した際、法定の支払い期日が存在することはご存知でしょうか? 今回は、下請け業者に対する支払い期日について説明します。 関係法令について 「支払い期日」に関して、関係する法律をご存知でし ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】監理技術者証の発行方法について
監理技術者証が必要だが、発行方法がわからないというお声を耳にします。 監理技術者証の発行について簡単に説明させていただきます。 監理技術者証が必要な場合 そもそも、監理技術者証が必要な場合とはどのよう ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】公共工事は必須?現場代理人とは
「現場代理人」という言葉を聞いたことはございますか? 「現場代理人」とは建設業法をある程度把握されている方や、公共工事を受注する建設業者であれば一度は耳にしたことがあるかと思います。 今回はこの現場代 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】配置義務のある専門技術者とは
建設業における「専門技術者」という言葉をご存知でしょうか? ○○技術者という言葉が建設業許可の中では多く使用されます。その中の「専門技術者」という技術者について説明します。 建設業許可とは そもそも、 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】個人事業主で経営経験が足りない場合の取得方法
新たに建設業許可を取得しようとする際に必要となる建設業に係る経営業務の管理責任者いわゆる「経営の経験」についてです。 この「経営の経験」という期間は建設業5年間です。 法人取得の場合は、基本的には建設 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】無許可業者との下請け契約に生じるリスク
本ページでは、建設業許可も取得していないいわゆる無許可業者との下請け契約で生じうる法的リスクについてお伝えします。 まず、前提情報として、「無許可業者」とは、建設業を営業するために必須の許可ではござい ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】国の許可 国土交通大臣許可とは 知事許可との違い
建設業許可には知事許可と国土交通大臣許可というものがあります。 よくあるお問い合わせとして、 「知事許可を取得した後に、他県の工事の請負いをしたいが他県の許可も必要でしょうか?」 というものです。 例 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】特定建設業許可とは 一般建設業許可との違い
建設業に関わる方であれば、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という許可を一度は聞いたことがあるかと思います。 今回は、この二つの許可の違いを説明します。 一般建設業許可 請負金額500万円以上の工 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】特定建設業許可における指導監督的実務経験とは
特定建設業許可の取得をする際によく耳にする営業所技術者(専任技術者)の要件でもある「指導監督的実務経験」についてです。 特定建設業許可については、一般建設業許可の要件と比較すると審査上、要件が厳格なも ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】配置技術者における監理技術者とは
建設業許可をもつ建設業者は請負った工事の現場に配置技術者を置かなければいけません。 配置技術者は工事の内容により、「主任技術者」または「監理技術者」を置かなければなりません。 本コラムでは、「監理技術 ...
続きを見る
-

-
【CCUS】技能者登録と能力評価手続のワンストップ化
建設キャリアアップ(CCUS)における技能者登録と能力評価手続きが令和7年3月に変わります。 従来、建設キャリアアップ(CCUS)における技能者登録を未登録の場合は、技能者登録を行った後に能力評価手続 ...
続きを見る
-

-
建設工事の請負契約書は分割して500万円越えなければ許可不要!?
建設業許可の必要なラインのひとつとして工事金額が500万円という基準があります。 いざ、工事金額が500万円を超えそうな場合によく聞く内容が「請負契約書を分割して1件あたり500万円に満たないようにす ...
続きを見る
-

-
【CCUS】建設キャリアアップシステムの運用費用はいくら?
建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入をお考えの方は運用費用、コスト気になるところかと思います。 建設キャリアアップシステム(CCUS)を導入する際に、一体いくらの費用がかかるのかを以下にまとめ ...
続きを見る
-

-
【法改正2025.2.1】特定建設業許可等の金額要件の見直し
法改正の背景 近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件について見直されることとなりました。 また、技術検定についても、人件費の高騰等を踏まえ、受検手数料について見直す ...
続きを見る
-

-
【監理技術者等の専任性】専任特例1号、専任特例2号とは
令和6年12月13日改正の建設業法に伴い、監理技術者等の専任性に関する内容が一部見直されました。 従来、監理技術者の専任が求められる工事において一定の要件を満たす監理技術者補佐を現場配置することにより ...
続きを見る
-

-
【法改正2024.12.13】建設業における技術者の専任義務の合理化 緩和について
技術者の専任義務 近年、工事現場におけるデジタル技術の活用(タブレット端末を通じた工事関係者間における設計図面や現場写真などの共有や、 現場作業員が装備するウェアラブルカメラなどを通じた監理技術者等と ...
続きを見る
-

-
【CCUS】建設キャリアアップシステムとは メリットとデメリット
CCUS(建設キャリアアップシステム)とは CCUS(建設キャリアアップシステム)とは、簡単に説明をすると 技能者ひとりひとりの経験やスキルを正確に把握する仕組みのことです。 技能者の以下の情報などを ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】主たる営業所・従たる営業所(本店・支店)とは 違い
本ページは、建設業許可における営業所(主たる営業所、従たる営業所)について解説します。 建設業許可における主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)の違いはどのようなものか、 また、従たる営業所(支店 ...
続きを見る
-

-
【建設業】石綿(アスベスト)事前調査結果報告の義務化について
令和4年4月1日から、一定規模の建築物などの解体・改修工事を行う施工業者は、 該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。 事前調査の対象 石綿含有の有無 ...
続きを見る
-

-
建設業で法人化(法人成り)をする時に気を付ける注意点5選
個人事業主で建設業を営んでいて、「そろそろ法人化(法人成り)したい」「法人化(法人成り)して建設業許可を取りたい」 とかんがえて、法人化(法人成り)する場面があると思います。 法人を設立する際は、様々 ...
続きを見る
-

-
【立入検査】建設業者に対して実施される立ち入り検査とは
建設業における「立入検査」というものをご存じですか? 建設業法第31条では、以下のように規定されています。 (報告及び検査) 第31条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、 ...
続きを見る
-

-
【熱絶縁工事業】建設業許可「熱絶縁工事業」の許可を取得する方法
熱絶縁工事業とは 熱絶縁工事業とは、以下のものとされています。 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 ・具体的には、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレ ...
続きを見る
-

-
【さく井工事業】建設業許可「さく井工事業」の許可を取得する方法
さく井工事業とは さく井工事業とは、以下のものとされています。 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 ・具体的には、さく井工事、観測井工事、還元井 ...
続きを見る
-

-
【清掃施設工事業】建設業許可「清掃施設工事」の許可を取得する方法
清掃施設工事業とは 清掃施設工事業とは、以下のものとされています。 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ・具体的には、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などの工事 清掃施設工事業許可が必要な場 ...
続きを見る
-

-
【造園工事業】建設業許可「造園工事業」の許可を取得する方法
造園工事業とは 造園工事業とは、以下のものとされています。 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 ・具体的には ...
続きを見る
-

-
【建具工事業】建設業許可「建具工事業」の許可を取得する方法
建具工事業とは 建具工事業とは、以下のものとされています。 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 ・具体的には、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッ ...
続きを見る
-

-
【水道施設工事業】建設業許可「水道施設工事」の許可を取得する方法
水道施設工事業とは 水道施設工事業とは、以下のものとされています。 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 ・具体的 ...
続きを見る
-

-
【解体工事業】建設業許可「解体工事業」の許可を取得する方法
解体工事業とは 解体工事業とは、以下のものとされています。 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ・具体的には、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などの工事 解体工事業許可が必要な場合とは 1件 ...
続きを見る
-

-
【消防施設工事業】建設業許可「消防施設工事」の許可を取得する方法
消防施設工事業とは 消防施設工事業とは、以下のものとされています。 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 ・具体的には、屋内消火栓設置工事、ス ...
続きを見る
-

-
【熱絶縁工事業】建設業許可「熱絶縁工事業」の許可を取得する方法
熱絶縁工事業とは 熱絶縁工事業とは、以下のものとされています。 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 ・具体的には、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレ ...
続きを見る
-

-
【機械器具設置工事業】建設業許可「機械器具設置」許可の取得方法
機械器具設置工事業とは 機械器具設置工事業とは、以下のものとされています。 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 ・具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事 ...
続きを見る
-

-
【防水工事業】建設業許可「防水工事業」の許可を取得する方法
防水工事業とは 防水工事業とは、以下のものとされています。 アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事 ・具体的には、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水 ...
続きを見る
-

-
【塗装工事業】建設業許可「塗装工事業」の許可を取得する方法
塗装工事業とは 塗装工事業とは、以下のものとされています。 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 ・具体的には、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事 ...
続きを見る
-

-
【電気通信工事業】建設業許可「電気通信」の許可を取得する方法
電気通信工事業とは 電気通信工事業とは、以下のものとされています。 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 ・具体的には、有線電気通 ...
続きを見る
-

-
【内装仕上工事業】建設業許可「内装仕上」の許可を取得する方法
内装仕上工事業とは 内装仕上工事業とは、以下のものとされています。 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 ・具体的には、イ ...
続きを見る
-

-
【鋼構造物工事業】建設業許可「鋼構造物」の許可を取得する方法
鋼構造物工事業とは 鋼構造物工事業とは、以下のものとされています。 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 ・具体的には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク ...
続きを見る
-

-
【ガラス工事業】建設業許可「ガラス工事業」の許可を取得する方法
ガラス工事業とは ガラス工事業とは、以下のものとされています。 工作物にガラスを加工して取付ける工事 具体的には、ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事などです。 ガラス工事業許可が必要な場合とは ...
続きを見る
-

-
【しゅんせつ工事業】建設業許可「しゅんせつ」の許可を取得する方法
しゅんせつ工事業とは しゅんせつ工事業とは、以下のものとされています。 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゅんせつ工事業許可が必要な場合とは 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を ...
続きを見る
-

-
【板金工事業】建設業許可「板金工事業」の許可を取得する方法
板金工事業とは 板金工事業とは、以下のものとされています。 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 具体的には、板金加工取付け工事、建築板金工事などです。 板金 ...
続きを見る
-

-
【舗装工事業】建設業許可「舗装工事業」の許可を取得する方法
舗装工事業とは 舗装工事業とは、以下のものとされています。 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 ・具体的には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブ ...
続きを見る
-

-
【鉄筋工事業】建設業許可「鉄筋工事業」の許可を取得する方法
鉄筋工事業とは 鉄筋工事業とは、以下のものとされています。 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 ・具体的には、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 鉄筋工事業許可が必要な場合とは 1件の請負代 ...
続きを見る
-

-
【タイル・れんが ・ブロック工事業】建設業許可を取得する方法
タイル・れんが・ブロツク工事業とは タイル・れんが ・ブロック工事業とは、以下のものとされています。 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイ ...
続きを見る
-

-
【電気工事業】建設業許可「電気工事業」の許可を取得する方法
電気工事業とは 電気工事業とは、以下のものとされています。 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 具体的には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、 構内電気設 ...
続きを見る
-

-
【屋根工事業】建設業許可「屋根工事業」の許可を取得する方法
屋根工事業とは 屋根工事業とは、以下のものとされています。 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 ・具体例は、「瓦」、「スレート」、「金属薄板」、「板金屋根工事」、「屋根断熱工事」 ・屋根一体 ...
続きを見る
-

-
【石工事業】建設業許可「石工事業」の許可を取得する方法
石工事業とは 石工事業とは、以下のものとされています。 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 具体的には、石積み( ...
続きを見る
-

-
【左官工事業】建設業許可「左官工事業」の許可を取得する方法
左官工事業とは 左官工事業とは、以下のものとされています。 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 具体的には、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工 ...
続きを見る
-

-
【大工工事業】建設業許可「大工工事業」の許可を取得する方法
大工工事業とは 大工工事業とは、以下のものとされています。 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 具体的には、大工工事、型枠工事、造作工事などです。 大工工事業 ...
続きを見る
-

-
【土工一式工事業】建設業許可「土木工事業」の許可を取得する方法
土木一式工事業とは 土木一式工事業とは、以下のものとされています。 ・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) とび・土工工事業の土木工 ...
続きを見る
-

-
【とび・土工】建設業許可「とび・土工工事」の許可を取得する方法
とび・土工工事業とは とび・土工工事業とは、以下のものとされています。 ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 とび工事、ひき工事、足場等仮 ...
続きを見る
-

-
【建築工事業】建設業許可「建築一式工事業」の許可を取得する方法
建築一式工事業とは 建築一式工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。 イメージ的は、「新築一棟の建築工事」というものが想像しやすいのではないでしょうか。 この、 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】建築一式工事?公共工事で入札の際はご注意下さい
公共工事に参入されている建設業者さまにご注意いただきたいことをお伝えします。 通常の請負工事の際はおそらくケースとしては少ないのですが、 公共が発注する工事の場合、工事の入札は工事の業種ごとに行われま ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】建設業許可を行政書士に依頼するメリットとは
建設業許可を取得している建設業者であれば「行政書士」と聞くと建設業許可の代行申請をしてくれる先生だというイメージではないでしょうか。 建設業許可を行政書士に依頼することでのメリットやデメリットをご紹介 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】建設業許可を取得したら金看板のご準備を!掲示義務
建設業許可を取得したら営業所にあこがれの「金看板」を掲げたい!と思われるかと思います。 建設業許可と言ったら金看板!逆に「金看板」は建設業許可の代名詞と言っても過言ではありません。 建設業法上、金看板 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】建設業許可の取得のタイミング、時期はいつがいい?
建設業許可を取得するタイミングでお悩みの方も多いかと思います。 建設業を営むにあたっては決して必須条件では無いがゆえに取得するタイミングや時期はいつが良いのか というお悩みについてお話します。 建設業 ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】建設業許可の取得には経営者の経験が必要?
建設業許可を新たに取得していきたいとお考えの方は一度は聞いたことがあると思います。 建設業許可の要件として、経営者としての経験が一定の年数必要であるということです。 建設業許可を取得するためのいくつか ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】意外な落とし穴?許可申請時に確認すべき重任登記
建設業許可申請を行う際に必ず提出、もしくは提示する必要がある会社の「登記事項証明書」 今回はこの登記事項証明書について説明させていただきます。 そもそも「登記事項証明書」とは、会社を設立する際に情報を ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】建設業許可取得のための要件(条件)とは簡単に説明
建設業許可をこれから取得しようとお考えの方や、建設業許可を取得するためのいくつかの要件につまづいている方向けに建設業許可取得のための要件をまとめさせて頂きました。 紹介するいくつかの要件の判断基準はあ ...
続きを見る
-

-
【建設業許可】建設業の無許可営業は違法となる?気になる建設業法
世の中には多くの「許可」が存在します。 その中でも建設業の許可についてです。 建設業許可の無許可営業は違法なのか。 結論から申し上げますと、無許可営業が直ちに違法とはなりません。 なぜなら建設業法(施 ...
続きを見る
-

-
【産業廃棄物収集運搬業】排出事業場の限定品目(業種指定)とは
廃棄物は、大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。 この「産業廃棄物」は更に品目が20種類に分類されています。 その20種類の内訳、詳細はこちらをご参照ください。 産業廃棄物は基本的に ...
続きを見る
-

-
【建設業法】建設業許可を失効してしまったらどうなる?
建設業許可を取得したら、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。 許可取得後の5年後ということもあり、ついうっかり更新手続きを忘れてしまうこともあります。 またこの他にも許可有効期間中に「欠格要件」 ...
続きを見る
-

-
【建設業】工事請負契約書とはいったいどのようなものか
建設工事の請負契約での契約書の作成は建設業法上の義務です。 建設業法第十九条 (建設工事の請負契約の内容) 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、 契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に ...
続きを見る
-

-
【法改正】建設業法及び入契法の一部改正についての閣議決定
2024年3月8日に、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 国土交通省より、改正法律案が発表されました。国交省HP ※閣議決定の ...
続きを見る
-

-
【建設業】2024年問題から考える「不適正な工期が与える現場への影響」について
働き方改革による施策のひとつでもある時間外労働時間の削減。 このことによって労働者にとって働きやすい環境の整備をして人材不足を改善していこうというのが目的です。 しかしながら、現実はどうでしょうか。様 ...
続きを見る
-

-
【入札参加資格申請】愛知県令和6・7年度の入札参加資格申請の定時受付が始まりました。
経営事項審査を受ける主の目的でもあります、入札への参加です。 愛知県内の公共団体の場合は一部例外はありますが、2年に一度定時受付という形で入札参加資格申請を受け付けています。 かと言って、2年に一度し ...
続きを見る
-

-
【建設業】良いことだけじゃない!建設業許可のデメリット3選!
建設業許可を取得すると、良いことつまりメリットが多くあります。このことは別ページにて説明もしました。 まとめると、以下の5つです。 メモ 対外的に社会的信用を得られる。 税込み500万円以上の工事の受 ...
続きを見る
-

-
【建設業】今後の業界のあり方について「要点3つ」にまとめて説明
建設業界は今後、働きかた改革に伴い働きやすい環境作りのため環境の整備が問われます。 そこで、今回はそれらに伴い、業界としての在り方について要点をまとめてお伝えします。 適正な工期、長時間労働の改善 働 ...
続きを見る
-

-
【建設業】建設業界の今後の流れを「時流を踏まえて考察3点」説明
建設業は、今の我が国にとってなくてはならない業界の存在です。いわゆる社会的インフラとも言える業界です。 そのため、管轄する国の機関でもある国土交通省の考え方を踏まえて考察していきます。 最初に申し上げ ...
続きを見る
-

-
【建設業】建設業許可業者の事業承継(相続)について注意点を解説
事業承継という言葉をご存じでしょうか?事業承継とは、とある会社を他の会社にその事業を売買などにより引き継いでもらうことです。 建設業許可に関わることでよくあるケースでいえば、個人事業主から法人成りした ...
続きを見る
-

-
建設業は下請けに仕事の丸投げは禁止!重層下請構造の禁止
(一括下請負の禁止) 第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け ...
続きを見る
-

-
建設業や産業廃棄物処理業に欠かせないダンプ車の土砂禁止車両
建設業や、産業廃棄物業ではダンプ車両を使用することがあるかと思います。 ダンプ車には2種類存在することはご存知ですか?それは、「土砂」を積載することが可能かどうかです。 ではなぜ、土砂の積載を禁止する ...
続きを見る
-

-
【建設業】10選!こんな取引条件には注意!公正な取引で健全に
【参考】建設業法 建設業での取引での注意すべき取引をご紹介します。 文章だけ読むと、いろいろと納得できるものが多いと思いますが、実際の現場での取引では案外存在するかもしれません。 もし自社にそのような ...
続きを見る
-

-
【建設業】10選!こんな取引条件には注意!取引先の見直しも必要?
建設業法はこちらをご参照ください。 やり直し工事費用の一方的な押し付け ・やり直し工事となった責任や費用を明確にしないまま、元請負人が下請負人に費用を一方的に負担させた場合 ・下請負人の責めに帰するこ ...
続きを見る
-

-
忘れてしまいがち注意!よくある建設業許可における変更手続き
1 欠格要件に該当 許可の要件で、絶対に落としてはならない「欠格要件」この欠格要件に一つでも当てはまってしまうと、許可は取れません。 建設業法の第8条です。 2 経営管理責任者要件が難しい 用語的には ...
続きを見る
-

-
建設業許可における専任技術者と配置技術者は出向者でも良いのか
専任技術者と主任技術者(主任技術者・監理技術者)は自社従業員でなければならないのかという疑問を感じたことはございませんか? 今回は、外部からの出向者でも選任でもよいのかという点で考えていきます。 出向 ...
続きを見る
-

-
令和5年7月から!建設業許可における専任技術者の要件が緩和
現在の専任技術者の選任要件は以下の通りです。 メモ ①建設業における国家資格等がある ②指定学科の大学卒業後3年の実務経験がある ③指定学科の高校卒業後5年の実務経験がある ④国土交通大臣が個別に認定 ...
続きを見る
-

-
建設業界に女性の雇用促進!働きやすい環境を整備して継続雇用
建設産業における女性の定着促進に向けた取組について詳しくはコチラ 背景 国土交通省と建設業5団体((一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会、(一社)全国中小建設業協会、(一社)建設産業専門団体 ...
続きを見る
-

-
【建設業】一人親方インボイスについて 鹿島建設株式会社の発表
令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります。 そこで、鹿島建設株式会社が先日ホームページにて発表した関係する記事をもとにお伝えします。 インボイス制度については、別ページを参考にしてください ...
続きを見る
-

-
【建設業】2024年問題について 大きな課題をまとめ、今後の建設業界を見据えて分析
そもそも2024年問題とは 2024年問題とは、働き方改革による制度のことで、2024年4月から労働者がいかに働きやすい環境にするかという制度が始まります。(厳密にいえば、建設業界は猶予期間があったの ...
続きを見る
-

-
【建設業】決算報告(事業年度終了報告)について 建設業法上の義務
決算報告、事業年度終了報告とは 決算報告、事業年度終了報告は建設業者さまであればご存じだと思います。 毎年一回、事業年度が終了した後に4か月以内に許可権者に対して施工工事、決算の報告を行うものです。 ...
続きを見る
-

-
【建設業法】2023年度改正点について 見落としがちな項目を説明
建設業経理士について 2023年4月から、経営事項審査(経審)における加点方法が変わりました。 従来(2023年3月)の経営事項審査(経審)での「その他の審査項目」において建設業経理士の有資格者の継続 ...
続きを見る
-

-
【建設業】キャリアアップシステム(CCUS)の経審における取り扱い
キャリアアップ(CCUS)とは 建設業キャリアアップシステムとは、簡単に説明すると事業者や技術者の就業履歴をシステム管理することによって事業者の技術者スキルレベルの管理や技術者個人のスキルや経験の見え ...
続きを見る
-

-
【建設業】大臣認定 常勤役員等(経管)、専任技術者要件
建設業許可の新規許可の取得や、新たな業種を追加する業種追加許可などといった際に、必ず必要となってくる要件の中に、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、その業種における専任技術者の配置が義務付けられていま ...
続きを見る
-

-
建設業許可とは?一定の規模の工事を行う事業者は必要
建設業とは、イメージ的なもので言えば主に建物を建てたり、修繕したり、それらに付随した工事業務のことをいいます。 大きな物を作るお仕事なので、それなりの資材や、道具、機械も要るので資金も必要です。 ある ...
続きを見る
-

-
建設業許可とは一体どんなものなのか。建設業許可を取得したい方へ
建設業法の定める建設業の業種は2種類の一式工事と27種類の専門工事に分類されています。 建設業における業種 ①土木一式②建築一式③大工④左官⑤とび・土木・コンクリート ⑥石⑦屋根⑧電気⑨菅⑩タイル・れ ...
続きを見る
-

-
建設業許可の取得要件6つ「これだけは絶対必要!」
経営業務の管理を適正う行うに足りる能力を有するものがいること 経営管理者と呼ばれるものです。 現在は、「常勤役員等」と呼ばれるものです。建設業許可を取得しようとする者(法人、個人事業主)はこの経営業務 ...
続きを見る
-

-
建設業許可の区分の大臣許可と知事許可とは。違いを簡単解説
建設業の許可には、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。 簡単に言うと、どこへの許可が必要か、ということです。国か、都道府県かということです。 ①2つ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業 ...
続きを見る
-

-
建設業許可の区分の一般建設業許可と特定建設業許可とは
建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。 一般建設業、特定建設業の違いは簡単に説明すると、 元請けとして、下請けに出す工事金額がいくらかということです。 ①工事を元請けとして下 ...
続きを見る
-

-
はじめて建設業許可を取得しましたが建設業許可に有効期間はあるの?
建設業の許可を取得すると、ずっとその許可は有効になるのか。 建設業の許可の有効期間は、5年間です。 つまり、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 失効ということは、受けていた許可が、無くなっ ...
続きを見る
-

-
建設業許可の後に必要な届出 どんな時に、いつまでに必要なのか
許可後に、必要な届出は以下のとおりです。 ①事業年度が終了したとき ②定款に変更が生じたとき ③使用人数の変更が生じたとき ④健康保険等の加入状況に変更が生じたとき ⑤常勤役員等に変更が生じたとき ⑥ ...
続きを見る
-

-
建設業許可の要件の一つ「専任技術者」とは どんな要件か
建設業許可の取得要件として、専任技術者の配置が必須です。 では、専任技術者とはいったい何なのか。 専任技術者は、建設業を営業する営業所に必ず配置しなければならない技術者です。 言葉のとおり、その営業所 ...
続きを見る
-

-
工事現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)の技術者とは
配置技術とは施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に 従事する者への指導監督をする現場のリーダーです。 ・主任技術者 ・監理技術者 の二種類があります。 主任技術者 主任 ...
続きを見る
-

-
建設業許可における最重要項目!?経営業務の管理責任者(経管)要件
建設業許可の取得のために必要な要件の一つとして、 経営業務の管理責任者(経管)の配置が必須です。 文字のごとく経営に関する責任者のことで、許可申請用語では常勤役員等という言葉にもなります。 経営業務の ...
続きを見る
-

-
建設業許可でよく確認される「常勤性」とは何が求められるのか
そもそも「常勤」という言葉の定義とは 「その勤務先等において、休日、その他勤務を要しない日を除き、 一定の計画のもとに毎日、所定の時間中、その職務に従事している」 ことを言います。 つまり、その勤務先 ...
続きを見る
-

-
建設業許可29業種のうち2つの「一式工事」専門業種と何が違うか
一式工事とは 一式工事は、29業種の工事許可業種 のうち、「建築一式工事」と 「土木一式工事」に分かれます。 他の27業種とは違い、 言葉のとおり「一式」の工事です。 また、建築一式工事の場合、 許可 ...
続きを見る
-

-
未登録や無許可業者は違法!?解体工事業は登録制度があります!
建設業には、29業種の許可が存在します。 許可を必要とする工事は簡単に説明すると 請負金額が税込み500万円以上の工事です。 しかし、「解体工事」は税込み500万円未満の工事 であっても“登録”がされ ...
続きを見る
-

-
【建設業】共同企業体(JV)とは?どういう意味?
「共同企業体と何ですか?」 という疑問が生まれることがあります。 建設業の許可業者であれば、決算月を基準に決算 とともに工事経歴書も作成すると思います。 その工事経歴書にも記載の場所があると思いますし ...
続きを見る
-

-
「ダンプ車の届出はお済みですか?」大型ダンプ車両は届出が必要
土砂等を運搬する大型自動車の届出(ダンプゼッケン届出)というものをご存じですか? 建設業、運送業、産業廃棄物収集運搬業などダンプ車を使用する業種の事業者の方は届出が必要となる場合がありますのでご確認く ...
続きを見る
-

-
【特定建設業】金額要件が変更!要件の変わった背景も踏まえて説明
一般建設業と特定建設業の違いを皆さまご存知でしょうか? 一般建設業を取得すべき業者は、税込500万円(一式工事の場合は、1,500万円)以上の工事の受注です。 特定の場合は、税込4,000万円(一式工 ...
続きを見る
-

-
【特定建設業】専任技術者の要件とは 一般建設業と比べ厳格な要件
まず特定建設業とは 4,500万円以上の工事を元請として更に下請けに出すかどうかが大きな判断基準です。 専任技術者の要件の違い 一般建設業と特定建設業で専任技術者の選任要件で何が違うのかというと、ずば ...
続きを見る
-

-
【5選】建設業許可を取得すると得られるメリット!
建設業許可を取得するメリット5選の紹介です。 1 会社の信用度の向上 建設業許可を取得するには様々な要件が存在します。 常勤役員等、専任技術者、資金要件、事務所要件、その他欠格要件と様々です。 許可の ...
続きを見る
-

-
常勤役員等【経営業務の管理責任者】建設業法施行規則第七条第一号
経営業務の管理責任者、通称、経管(けいかん)とは、建設業許可における要件のもっとも重要なものといっても過言ではありません。 建設業許可の用語的には、2020年に「常勤役員等」という言葉に変わりました。 ...
続きを見る
-

-
【まとめ】特定建設業における資金要件 厳格な要件があります!
特定建設業の許可を取得したい場合は、一般建設業との違いで資金要件がいくつか存在します。 次に掲げる要件の1つでも満たさない場合は、許可を受けることができません。 ① 欠損の額が資本金の額 ...
続きを見る