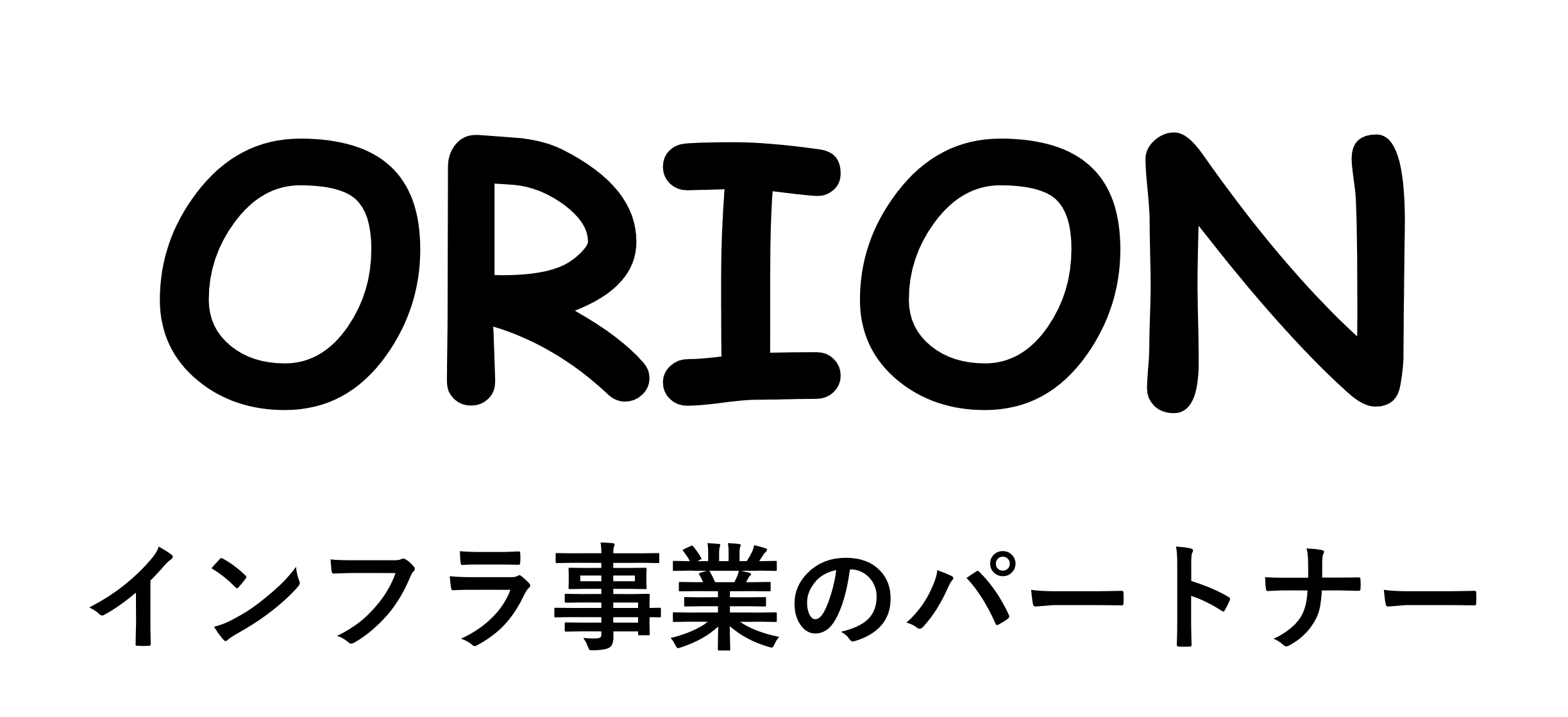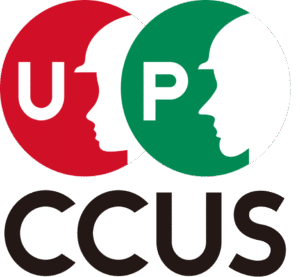本ページでは、建設業許可も取得していないいわゆる無許可業者との下請け契約で生じうる法的リスクについてお伝えします。
まず、前提情報として、「無許可業者」とは、建設業を営業するために必須の許可ではございません。
500万円(建築一式の場合は1,500万円)以上の建設工事を請負うために必要なる許可制度です。
Skip to Contents
建設業許可が必要な場合
先述のように建設業許可というものは全ての建設工事を請負うことが対象ではございません。
・請け負う工事金額が500万円(建築一式の場合は1,500万円)以上となる場合です。
では、この金額における注意点についてお話しします。
500万円の内訳
この「500万円以上」という金額には何が含まれるのかを確認していきましょう。
・人件費(人工)
・材料費
・消費税
・その他経費
・附帯工事
・追加工事
これらが主な内訳となります。
材料費
よく勘違いが起こるこの材料費、下請け契約が主となる建設業者の場合、「材料は全て元請けからの支給だから大丈夫です」
と思われている方がみえます。しかし、この「材料費」にあっては自社手配、元請け支給であっても同様です。
元請け支給だから材料費がわからない場合でも、計算上は市場価格にて判断します。
附帯工事
例えば、造成工事を請負った中に地中の配管の施工をする場合です。
このようなケースですと、造成工事のみならず、管工事の工事費用ももちろん含まれます。
請負った工事業種のみで考えないように注意しましょう。
追加工事
こちらもよく相談を受けます。
「工事契約書を分割して500万円未満にすれば建設業許可は不要ですよね?」
1つの建設工事の受注から追加工事が発生した場合は同一工事とみなし工事金額ももちろん合算されます。
契約書基準ではなく、工事の現場位置、工期、内容、一体性など総合的に勘案し判断されますのでご注意ください。
無許可業者への発注リスク
先述のように建設業許可が必要な工事がどのようなものかは理解できたと思います。
材料費を支給して500万円未満に調整をしても、契約書を分割しても実態で判断されます。
仮に400万円の無許可業者と下請契約を交わした際に、追加工事が発生して500万円を超えてしまうことは少なくありません。
材料費に関しては、自社が製造業などのメーカーを兼ねている場合は、材料費が大半を占めることも少なくありません。
法的リスク
建設業法では以下の条文も存在します。【建設業法】
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
このように罰則も設けられています。
罰則を受けてしまうと、建設業許可上の「欠格要件」に該当してしまい、最悪の場合許可の取り消し処分となりえます。
許可の取り消し処分となってしまった場合は、改めて許可を取得するには5年経過しなければ「欠格要件」が無くなりません。
また、許可の取消にならずとも、「営業停止処分」という処分にもなりえます。
条文を見て頂ければわかると思いますが、工事を請負った建設業者だけではなく、工事を発注した建設業者も処分や罰則の対象です。
対策案
無許可業者への不意な違法工事の発注の対策としては、
・下請契約時に必ず建設業許可証を確認する
または、
・国土交通省の許可業者検索サイトにて発注時に必ず確認する
(許可を取得して日が浅い場合は反映されていない場合がございます)
これらのいずれかは必ず行うようにしましょう。
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。